「元本保証」という言葉を聞くと、多くの人が「安心」「安全」といったイメージを抱くのではないでしょうか。特に、大切なお金を預ける預貯金において、元本保証は大きな魅力です。しかし、低金利が続き、物価上昇(インフレ)も気になる現在、「本当に預貯金だけで良いのだろうか?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
この記事では、「預貯金の元本保証は本当に良いのか?」という疑問に答えるため、預貯金の元本保証の仕組み、メリット・デメリット、そして他の選択肢との比較について詳しく解説します。ご自身の資産形成を考える上での参考にしてください。
そもそも預貯金の「元本保証」とは?
預貯金の「元本保証」とは、文字通り、預け入れた元本(お金そのもの)が減らないことを意味します。銀行や信用金庫などの金融機関は、預金保険制度によって保護されています。
- 預金保険制度: 万が一、金融機関が破綻した場合でも、預金保険機構が一定額まで預金者を保護する制度です。
- 保護の範囲: 1金融機関につき、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息が保護されます。(※当座預金や利息のつかない普通預金などは全額保護されます)
この制度があるため、私たちは比較的安心して金融機関にお金を預けることができます。
預貯金のメリット:安心感と使いやすさ
元本保証以外にも、預貯金には以下のようなメリットがあります。
- 高い安全性: 預金保険制度に守られており、元本割れのリスクが極めて低い点が最大のメリットです。大切なお金を「安全に保管する」という目的には非常に適しています。
- 高い流動性: ATMや窓口で、いつでも必要な時に現金を引き出すことができます。急な出費に対応しやすい点は大きな利点です。
- 手軽さ: 口座の開設や入出金の手続きが比較的簡単で、誰でも利用しやすい金融商品です。
預貯金のデメリットと注意点:増えない、目減りするリスクも
一方で、預貯金には注意すべきデメリットも存在します。
- 低金利: 現在の日本では、低金利が続いています。普通預金はもちろん、定期預金に預けても、得られる利息はごくわずかです。利息による資産増加は、ほとんど期待できない状況と言えるでしょう。
- インフレリスク: 預貯金の最大の弱点とも言えるのがインフレリスクです。インフレとは、物価が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がることです。
- 例: 年間の物価上昇率が2%で、預金金利が0.2%だとします。この場合、100万円を預けていても、1年後には利息が2,000円しかつかないのに対し、物価は2万円分上昇しています。つまり、実質的にはお金の価値が目減りしてしまっているのです。預貯金は額面上の元本は保証されますが、実質的な価値(購買力)は保証されない点に注意が必要です。
- 機会損失: 預貯金にお金を置いておくだけでは、他の投資方法(株式、投資信託など)で得られたかもしれないリターンを得る機会を逃している可能性があります。特に長期的な資産形成を考える場合、この機会損失は無視できません。
- 預金保険制度の限度額: 前述の通り、保護されるのは1金融機関あたり1,000万円とその利息までです。これを超える金額を一つの金融機関に預けている場合、万が一の際には全額が保護されないリスクがあります。
【結論】預貯金は「守る」には良いが、「増やす」には不向き
では、「預貯金の元本保証は本当に良いのか?」という問いに対する答えです。
- 「お金を安全に保管する」「いつでも使えるようにしておく」という目的においては、預貯金は依然として有効で、良い選択肢です。 特に、生活費や近々使う予定のあるお金(生活防衛資金など)は、安全性と流動性の高い預貯金で確保しておくのが基本です。
- しかし、「お金を増やす」「インフレに負けないように資産価値を守る」という目的においては、現在の低金利下では預貯金だけでは不十分であり、他の選択肢を検討する必要があります。
預貯金以外の選択肢との比較
元本保証やそれに近い安全性を持つもの、あるいはリスクを取ってリターンを目指すものなど、様々な金融商品があります。
| 種類 | 元本保証 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金・定期預金 | あり | 安全性・流動性が高い。 | いつでも引き出せる、元本割れリスク極小 | 低金利、インフレに弱い |
| 個人向け国債 | あり | 国が発行・元本保証。固定金利(3年・5年)と変動金利(10年)がある。変動10年は最低金利0.05%保証。 | 預金より金利が高い可能性、国が保証する安心感 | 発行から1年間は原則換金不可、金利上昇局面では魅力が薄れる可能性 |
| 投資信託 | なし | 運用のプロが複数の株式や債券などに分散投資。NISA/iDeCoなどの税制優遇制度を活用できる。 | 少額から分散投資可能、専門家に任せられる | 元本割れリスク、信託報酬などの手数料がかかる |
| 株式投資 | なし | 企業の株式を売買。値上がり益や配当金が期待できる。 | 大きなリターンが期待できる | 元本割れリスクが高い、企業分析などの知識が必要 |
| 貯蓄型保険 | (※) | 保険機能と貯蓄機能を併せ持つ。終身保険、養老保険、個人年金保険など。満期金や解約返戻金がある。 | 保障と貯蓄を兼ねられる | 早期解約時の元本割れリスク、予定利率が低い、手数料が高い傾向 |
(※)貯蓄型保険は、満期まで保有すれば支払った保険料以上の満期金を受け取れる商品もありますが、契約内容や解約時期によっては元本割れします。厳密な意味での元本保証とは異なります。
賢いお金の守り方・増やし方のヒント
預貯金のメリット・デメリット、そして他の選択肢を踏まえ、どのように資産と向き合えば良いのでしょうか。
- お金を目的別に色分けする:
- 生活防衛資金(3ヶ月~1年分の生活費): 病気や失業など、万が一の備え。安全性・流動性最優先で預貯金に。
- 近い将来使う予定の資金(数年以内): 住宅購入の頭金、車の購入費、教育費など。元本割れリスクを避けたいので、預貯金や個人向け国債などが候補。
- 長期的に増やすお金(10年以上先): 老後資金、余裕資金など。インフレに負けないよう、リスク許容度に応じて投資信託(NISA/iDeCo活用)や株式などを検討。
- インフレを意識する: 「預貯金だけでは目減りする可能性がある」という意識を持ち、資産の一部をインフレに強いとされる投資(株式、不動産などを含む投資信託など)に振り分けることを検討しましょう。
- 分散投資を心がける: 全ての資産を一つの金融商品に集中させるのではなく、預貯金、債券、株式など、値動きの異なる複数の資産に分散させることがリスク軽減につながります。
- 少額から始めてみる: 投資に不安がある方は、NISA(つみたてNISAなど)を活用して、月々数千円~1万円程度の少額から投資信託の積立を始めてみるのも良いでしょう。実際に経験することで、投資への理解が深まります。
- 情報収集と比較検討: 金融機関の窓口だけでなく、インターネットや書籍などで幅広く情報を集め、手数料やリスクなどを比較検討することが大切です。
まとめ
預貯金の元本保証は、私たちに大きな安心感を与えてくれます。お金を「安全に守る」という点では非常に優れた方法です。しかし、現在の低金利環境とインフレリスクを考えると、「お金を増やす」「資産価値を守る」という目的には、預貯金だけでは力不足と言わざるを得ません。
大切なのは、預貯金のメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身のライフプランやお金の目的、リスク許容度に合わせて、他の金融商品とバランス良く組み合わせることです。
「元本保証だから安心」と思考停止せず、インフレなどのリスクにも目を向け、ご自身のお金としっかり向き合い、賢い資産形成を目指しましょう。
【ご留意事項】
- この記事は、特定の金融商品を推奨するものではありません。
- 投資には元本割れのリスクが伴います。金融商品の選択や投資の判断は、ご自身の責任において行ってください。
- 税制や制度は変更される可能性があります。最新の情報をご確認ください。
この記事を書いた人:かんとりー(ファイナンシャルプランナー2級)
節約・投資・デジタル活用を中心に、暮らしに役立つ情報を発信中。
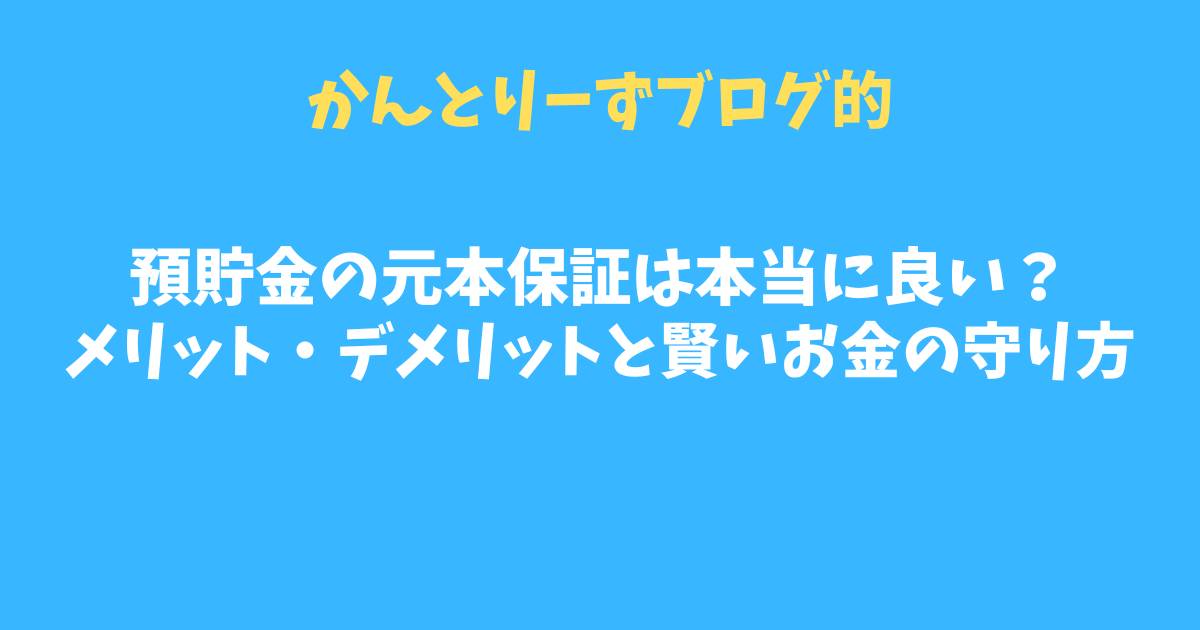
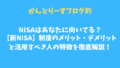
コメント