「NISAはやめた方がいい」 「NISAはやらない方がいいって本当?」
近年、NISA(少額投資非課税制度)は資産形成の有効な手段として注目されていますが、一方で上記のようなネガティブなキーワードでの検索も少なくありません。
NISAを始めようか迷っている方、あるいは既に始めているけれど「本当にこのままでいいのだろうか?」と不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、「NISAはやめた方がいい」という声がなぜ上がるのか、その理由となるNISAのデメリットや注意点を詳しく解説します。さらに、NISAをやめた方がいいかもしれない人の特徴、それでも多くの人にとってNISAが有効な理由、そしてやめる前に検討すべきことまで、網羅的にご紹介します。
この記事を読めば、NISAに対する漠然とした不安が解消され、ご自身の状況に合わせてNISAを続けるべきか、あるいは他の選択肢を検討すべきかの判断材料を得られるはずです。
この記事のポイント
- 「NISAはやめた方がいい」と言われる理由(デメリット・注意点)
- NISAをやめた方がいいかもしれない人の具体的なケース
- デメリットを理解した上で、それでもNISAがおすすめな理由
- NISAをやめる前に考えたいこと、やめる場合の手続き
そもそもNISAとは?簡単におさらい
本題に入る前に、NISA制度について簡単におさらいしておきましょう。
NISAは、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品(株式や投資信託など)から得られる利益(配当金、分配金、譲渡益)が非課税になる制度です。通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を利用すればそれがゼロになります。
2024年から始まった新NISAには、以下の2つの投資枠があります。
- つみたて投資枠: 年間120万円まで。長期・積立・分散投資に適した、金融庁が定めた基準を満たす投資信託が対象。
- 成長投資枠: 年間240万円まで。投資信託のほか、上場株式なども対象。
両方の枠を併用でき、年間最大360万円まで投資可能です。生涯にわたる非課税保有限度額は1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)で、非課税保有期間は無期限です。
なぜ「NISAはやめた方がいい」と言われる?デメリットと注意点
メリットの大きいNISAですが、「やめた方がいい」という声が上がるのには理由があります。主なデメリットや注意点を見ていきましょう。
- 元本保証がない(投資リスクがある) NISAはあくまで「投資」であり、預貯金とは異なります。購入した金融商品の価格は変動するため、運用がうまくいかなければ投資した元本を下回る(損をする)可能性があります。非課税になるのは利益が出た場合の話であり、損失が出た場合に補填されるわけではありません。
- 損益通算・繰越控除ができない 通常の課税口座(特定口座や一般口座)では、複数の金融商品の利益と損失を相殺する「損益通算」や、年間の損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して将来の利益と相殺できる「繰越控除」が可能です。しかし、NISA口座での損失は、他の口座の利益と損益通算したり、翌年以降に繰り越したりすることができません。NISA口座内で大きな損失が出た場合、税制上のメリットを受けられないことになります。
- 短期的な売買には不向き NISA、特に「つみたて投資枠」は、長期的な資産形成を目的とした制度設計になっています。頻繁に売買を繰り返すデイトレードのような短期的な投資スタイルには、手数料や非課税枠の観点からあまり向いていません。非課税枠は一度使うと、売却してもその年の枠は復活しません(翌年以降に再利用は可能)。
- 非課税枠には上限がある 新NISAでは年間投資枠が拡大されましたが、それでも年間360万円、生涯で1,800万円という上限があります。これ以上の金額を投資したい場合は、課税口座を利用する必要があります。
- 投資できる商品が限られている 特に「つみたて投資枠」で購入できる商品は、金融庁の基準を満たした投資信託に限られています。個別株式やREIT(不動産投資信託)、債券など、より多様な商品に投資したい場合は、「成長投資枠」や課税口座を利用する必要があります。
- 自分で商品を選ぶ必要がある(投資判断が難しい) NISAでは、どの金融機関で口座を開設し、どの商品に投資するかを自分で判断する必要があります。投資初心者にとっては、商品選びが難しく感じられたり、何から始めればいいか分からなかったりすることがあります。
- すぐに現金化できない場合がある(換金性) 投資信託などは、売却を申し込んでもすぐに現金化されるわけではなく、数日かかるのが一般的です。急にお金が必要になった場合に、すぐに対応できない可能性があります。
- 制度変更のリスク NISAは国の制度であり、将来的に制度内容が変更される可能性はゼロではありません。過去にも制度変更があったように、今後の税制改正などで内容が変わるリスクも考慮しておく必要があります。
NISAをやめた方がいいかもしれない人の特徴
上記のデメリットや注意点を踏まえると、以下のような方はNISAの利用を慎重に検討するか、あるいは「やめる」という選択肢も視野に入れた方が良いかもしれません。
- 投資リスクを全く許容できない人 「絶対に損はしたくない」「元本保証が第一」という考えの方には、価格変動リスクのあるNISAは向いていません。預貯金や個人向け国債など、より安全性の高い方法を検討しましょう。
- 生活防衛資金が十分にない人 投資はあくまで余裕資金で行うべきです。病気や失業など、万が一の事態に備えるための生活防衛資金(一般的に生活費の3ヶ月~1年分程度)が確保できていない場合は、まず貯金を優先しましょう。
- 近い将来(数年以内)に使う予定のお金で投資しようとしている人 住宅購入の頭金や教育費など、使う時期が決まっている資金をNISAで運用するのはリスクが高いです。必要な時期に価格が下落している可能性があり、予定通りに資金を使えなくなるかもしれません。短期~中期で使う予定のお金は、預貯金など安全な方法で確保しましょう。
- 損益通算や繰越控除を積極的に活用したい投資経験者 NISA口座の損失は損益通算・繰越控除の対象外です。様々な金融商品に投資し、税制上のメリットを最大限活用したいと考えている投資経験者にとっては、NISAのこの仕様がデメリットになる場合があります。
- 自分で投資判断をするのが苦手・面倒だと感じる人 商品選びや運用状況の確認などを自分で行うのが負担に感じる場合は、ロボアドバイザーや、専門家に相談できるサービス(IFAなど)の利用も検討しましょう。ただし、これらのサービスには別途手数料がかかる場合があります。
それでも多くの人にNISAをおすすめする理由
デメリットや注意点、そして「やめた方がいいかもしれない人」の特徴を挙げましたが、それでも多くの人にとってNISAは非常に有効な資産形成手段です。その理由を再確認しましょう。
- 運用益非課税のメリットは絶大 通常約20%かかる税金が非課税になる効果は、特に長期投資において非常に大きいです。複利効果と組み合わせることで、効率的な資産形成が期待できます。
- 少額から始められる 金融機関によっては月々100円から積立投資が可能です。まとまった資金がなくても、気軽に始められるのは大きなメリットです。
- 長期・積立・分散投資を実践しやすい 特に「つみたて投資枠」は、リスクを抑えながら長期的に資産を育てる「長期・積立・分散投資」に適した商品が選定されています。投資初心者でも始めやすい仕組みです。
- 新NISAで利便性が大幅向上 非課税保有期間が無期限化され、年間投資枠も拡大されたことで、より柔軟で長期的な視点での資産形成が可能になりました。売却すれば翌年以降に枠が復活する点も使いやすくなっています。
NISAをやめる前に検討すべきこと
「やっぱりNISAをやめようかな…」と考え始めたら、すぐに手続きを進める前に以下の点を検討してみましょう。
- 投資目的とリスク許容度の再確認: なぜNISAを始めたのか、どのくらいの期間で、どのくらいの資産を目指したいのかを再確認しましょう。また、どの程度のリスクなら受け入れられるのか(リスク許容度)も改めて考えます。目的や許容度が変化している可能性もあります。
- 投資方針や商品の見直し: 現在の投資商品が自分のリスク許容度や目的に合っているか確認しましょう。リスクを取りすぎていると感じるなら、より安定志向の商品に変更する、あるいは投資配分を見直すといった対策が考えられます。
- 積立額の変更・一時停止: 資金的に厳しい、あるいは相場の下落が怖いと感じる場合は、積立額を減額したり、一時的に積立を停止したりすることも可能です。完全にやめてしまう前に、負担を軽減する方法を探ってみましょう。
- 専門家への相談: ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家に相談し、客観的なアドバイスをもらうのも有効です。自分の状況に合った運用方法や、NISAを続けるべきかどうかの判断材料を得られます。
NISAをやめる場合の手続きと注意点
検討の結果、やはりNISAをやめる(口座を廃止する、または保有商品を売却する)と決めた場合の手続きと注意点です。
- 手続き: NISA口座を開設している金融機関に、口座廃止または保有商品の売却を申し込みます。具体的な手続き方法は金融機関によって異なるため、ウェブサイトやコールセンターで確認しましょう。
- NISA口座の廃止: NISA口座を廃止すると、その年の非課税枠は利用できなくなります。再開設も可能ですが、手続きに時間がかかる場合があります。
- 保有商品の売却: NISA口座内で商品を売却した場合、利益が出ていても非課税です。ただし、購入時よりも価格が下がっている場合は損失が確定します。売却せずに課税口座(特定口座や一般口座)に移管することも可能ですが、移管時の時価が新たな取得価額となり、その後の値上がり益には課税されます。
まとめ:「NISAはやめた方がいい」は本当?自分に合った判断を
「NISAはやめた方がいい」という意見は、NISAのデメリットや、特定の状況にある人にとっては当てはまる可能性があります。元本保証がないこと、損益通算ができないことなどの注意点を理解しておくことは非常に重要です。
しかし、運用益非課税という大きなメリットがあり、新NISAでは制度も拡充され、多くの人にとって長期的な資産形成に有効な制度であることも事実です。
「やめた方がいい」という情報に惑わされるのではなく、NISAのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の投資目的、リスク許容度、ライフプランと照らし合わせて、NISAを活用するかどうか、どのように活用するかを判断することが大切です。
勢いでやめてしまう前に、この記事を参考に、ご自身にとってNISAが本当に「やめた方がいい」ものなのか、じっくりと考えてみてください。
この記事を書いた人:かんとりー(ファイナンシャルプランナー2級)
節約・投資・デジタル活用を中心に、暮らしに役立つ情報を発信中。
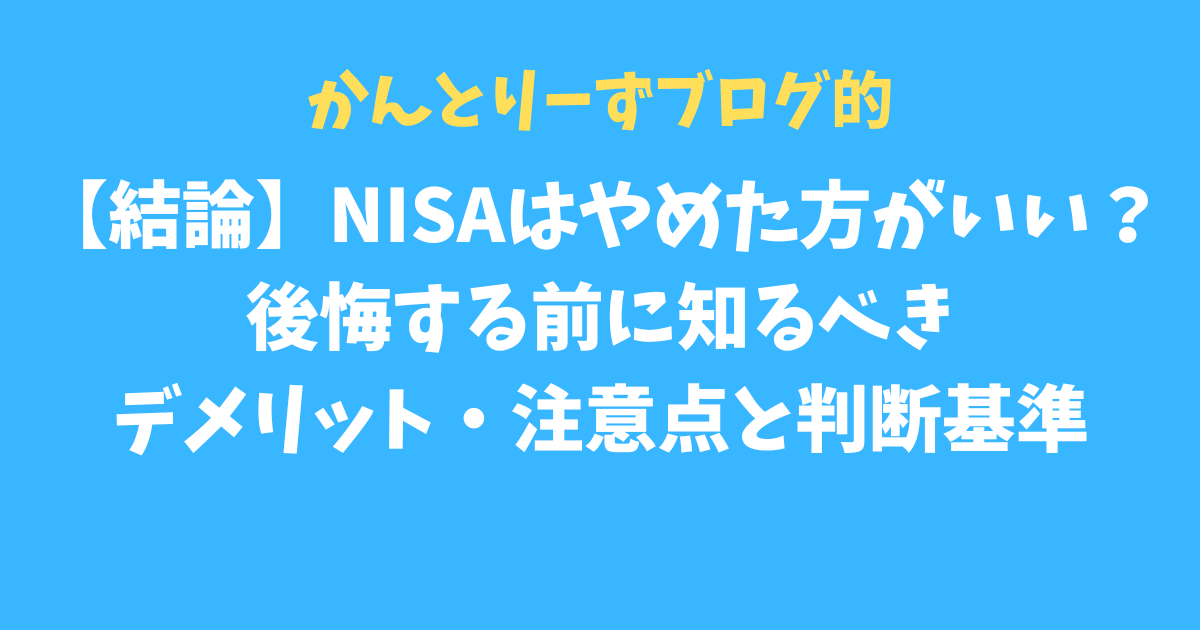
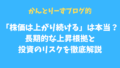
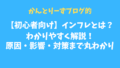
コメント