「共済組合の附加給付って、なんだか難しそう…」 「健康保険とは何が違うの?」 「自分にも関係あるのかな?」
公務員や特定の団体の職員などが加入する共済組合。その福利厚生の一つに「附加給付(ふかきゅうふ)」という制度があるのをご存知でしょうか?
これは、通常の健康保険(法定給付)にプラスして、共済組合が独自に支給してくれるお金のこと。知っているのと知らないのとでは、受けられるサポートに大きな差が出る可能性があります。
この記事では、共済組合の附加給付について、「名前は聞いたことあるけど、よく分からない…」という方に向けて、以下の点を分かりやすく解説します。
- 附加給付って、そもそも何?
- どんな種類の附加給付があるの?
- 附加給付のメリット・デメリットは?
- どうやって申請するの?
この記事を読めば、附加給付の基本が理解でき、ご自身に関係する給付があるかを確認するきっかけになるはずです。ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「共済組合」とは?
附加給付の話に入る前に、簡単に「共済組合」についておさらいしましょう。
共済組合は、主に国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが加入する、相互扶助を目的とした組織です。組合員の掛金(保険料)と事業主(国や地方公共団体など)の負担金によって運営され、組合員とその家族の病気、けが、出産、死亡、休業、災害などに対して必要な給付(お金の支給)を行います。
健康保険(協会けんぽや組合健保など)と似ていますが、共済組合は法律で定められた給付(法定給付)に加えて、**組合独自の「附加給付」**を行っている点が大きな特徴です。
「附加給付」とは?法定給付との違い
では、本題の「附加給付」について詳しく見ていきましょう。
附加給付とは、法律で定められた健康保険の給付(法定給付)に上乗せして、各共済組合が独自の規約に基づいて行う給付のことです。
| 種類 | 説明 | 根拠となるもの |
|---|---|---|
| 法定給付 | 法律(健康保険法など)で定められた、全国共通の基本的な給付 | 法律 |
| 附加給付 | 各共済組合が独自に定めて、法定給付に上乗せして行う、手厚い給付 | 各共済組合の規約 |
Google スプレッドシートにエクスポート
なぜ附加給付があるの?
これは、共済組合が組合員の福利厚生を手厚くし、相互扶助の精神をより具体化するために設けている制度だからです。法定給付だけではカバーしきれない部分を補い、組合員が安心して生活できるようサポートすることを目的としています。
重要な注意点
附加給付の内容(種類、支給額、支給条件など)は、加入している共済組合によって大きく異なります。「隣の部署の〇〇さんはもらえたのに…」ということが起こり得るのはこのためです。必ずご自身の加入している共済組合の情報を確認するようにしましょう。
どんな種類があるの?代表的な附加給付
附加給付には様々な種類がありますが、ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
- 一部負担金払戻金(いちぶふたんきん はらいもどしきん) / 家族療養費附加金(かぞくりょうようひ ふかきん)
- 内容: 病院などで支払った医療費の自己負担額(通常3割)が、一定額を超えた場合に、その超えた分(または一部)が払い戻される制度です。
- ポイント: 国の「高額療養費制度」とは別に、共済組合がさらに自己負担を軽減してくれる仕組みです。自己負担額の上限が、一般的な健康保険よりも低く設定されている場合が多いです。
- 傷病手当金附加金(しょうびょうてあてきん ふかきん)
- 内容: 病気やけがで仕事を休み、給料が支払われない場合に支給される「傷病手当金(法定給付)」に上乗せされる給付です。
- ポイント: 法定給付の支給期間(通常1年6ヶ月)が終了した後も、一定期間、給付が延長されたり、支給額が上乗せされたりすることがあります。長期間の療養が必要になった場合に非常に助かる制度です。
- 出産費附加金(しゅっさんぴ ふかきん) / 家族出産費附加金(かぞくしゅっさんぴ ふかきん)
- 内容: 出産時に支給される「出産育児一時金(法定給付)」に上乗せして支給されるお金です。
- ポイント: 出産にかかる費用負担をさらに軽減してくれます。
- 埋葬料附加金(まいそうりょう ふかきん) / 家族埋葬料附加金(かぞくまいそうりょう ふかきん)
- 内容: 組合員やその家族が亡くなった場合に支給される「埋葬料(費)(法定給付)」に上乗せして支給されるお金です。
- ポイント: 葬儀費用の負担を軽減してくれます。
- 訪問看護療養費附加金 / 家族訪問看護療養費附加金
- 内容: 訪問看護を利用した際の自己負担額に対して支給される附加給付です。
- ポイント: 在宅療養の経済的負担を軽減します。
これらはあくまで一例です。 上記以外にも、休業手当に関する附加給付や、人間ドックの補助など、様々な附加給付を設けている共済組合があります。
附加給付のメリット・デメリット
共済組合の附加給付には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 医療費や休業時の経済的負担が軽減される: 法定給付だけの場合に比べて、自己負担が少なく済んだり、休業中の収入が補填されたりします。
- 民間の医療保険などを検討する際の判断材料になる: 共済組合の保障が手厚い場合、民間の保険への加入を見送ったり、保障内容を絞ったりすることができます。
- 安心感につながる: 万が一の病気やけが、出産などに備えて、手厚いサポートがあるという安心感を得られます。
デメリット
- 共済組合によって内容や水準が異なる: 自分が加入している組合にどのような附加給付があるか、しっかり確認する必要があります。
- 制度が変更・廃止される可能性がある: 共済組合の財政状況などにより、将来的に附加給付の内容が変わったり、なくなったりする可能性もゼロではありません。
- 自動的に支給されない場合が多い: 多くの附加給付は、自分で申請手続きを行う必要があります。申請漏れがないように注意が必要です。
- 支給要件がある: 全ての組合員が必ず利用できるわけではなく、特定の条件を満たす必要があります。
附加給付はどうやって申請するの?
附加給付を受け取るためには、原則として申請が必要です。自動的に振り込まれるものは少ないので注意しましょう。
基本的な申請の流れ
- 確認: まず、ご自身が加入している共済組合のウェブサイトや担当窓口(人事課や総務課など)で、どのような附加給付があるか、支給要件、申請方法を確認します。
- 書類準備: 必要な申請書類を入手し、記入します。多くの場合、医療機関の領収書や、医師の証明書などが必要になります。
- 提出: 記入した申請書と必要書類を、共済組合の担当窓口に提出します。
- 審査・支給: 共済組合で審査が行われ、承認されると指定の口座に給付金が振り込まれます。
申請のポイント
- 早めに確認・申請する: 附加給付には申請期限が設けられていることが多いです。「気づいたら期限が過ぎていた…」とならないよう、給付の対象となる事由が発生したら、早めに確認・申請しましょう。
- 不明な点は必ず問い合わせる: 申請書類の書き方や必要書類など、分からないことがあれば、遠慮なく共済組合の担当窓口に問い合わせましょう。
まとめ:附加給付は共済組合員の強い味方!まずは確認を!
今回は、共済組合の「附加給付」について解説しました。
- 附加給付は、法定給付に上乗せされる共済組合独自の給付。
- 医療費負担の軽減や休業時の所得補償など、手厚いサポートが受けられる可能性がある。
- 内容は共済組合によって異なるため、ご自身の加入する組合の情報を確認することが重要。
- 多くの場合、申請が必要なので、忘れずに手続きを。
附加給付は、共済組合員ならではの大きなメリットの一つです。ご自身やご家族に万が一のことがあった場合に、どのようなサポートが受けられるのか、この機会にぜひ一度、加入している共済組合のウェブサイトや資料を確認してみてください。知っておくだけで、いざという時の安心感が大きく変わるはずです。
ディスクレイマー: この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の共済組合の制度内容を保証するものではありません。附加給付に関する最新かつ正確な情報は、必ずご自身が所属する共済組合にご確認ください。
この記事を書いた人:かんとりー(ファイナンシャルプランナー2級)
節約・投資・デジタル活用を中心に、暮らしに役立つ情報を発信中。
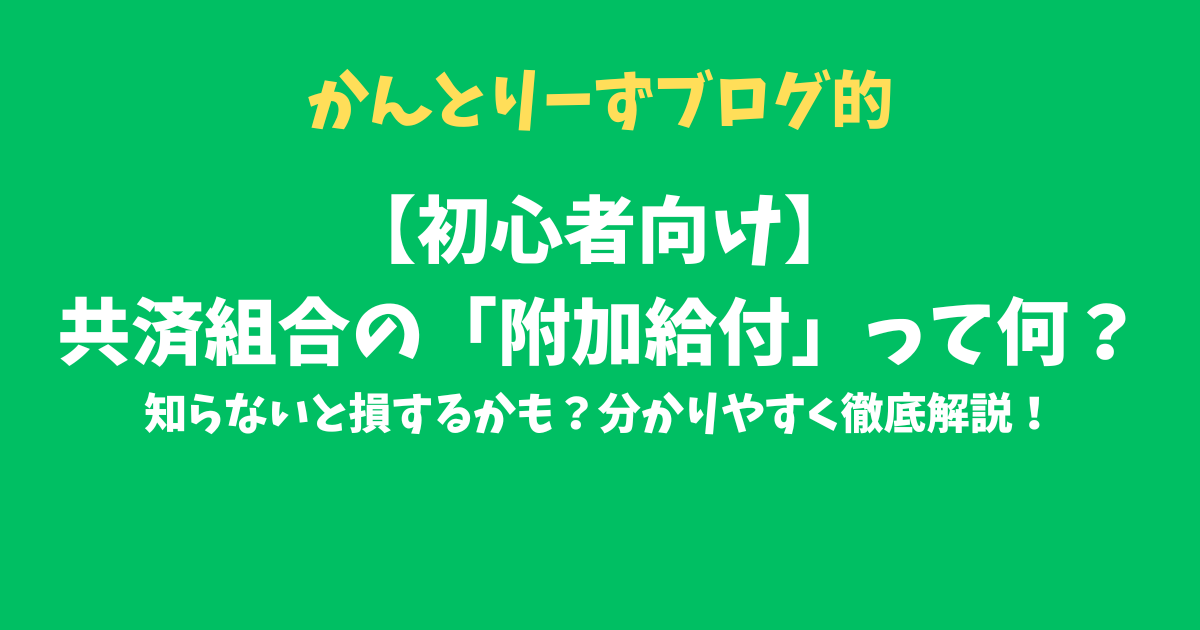
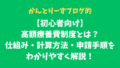
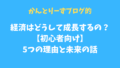
コメント