病気やケガで医療費が高額になると、家計への負担が心配になりますよね。そんな時に頼りになるのが**「高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)」**です。
この制度を知っているだけで、いざという時の経済的な不安を大きく減らすことができます。
この記事では、高額療養費制度について、以下の点を初心者の方にも分かりやすく解説します。
- 高額療養費制度って、そもそも何?
- 結局、いくらまで自己負担すればいいの?
- どうやって申請すればお金が戻ってくるの?
- 知っておくとお得なポイントは?
専門用語はなるべく避け、図や具体例を交えながら説明していきますので、ぜひ最後まで読んで理解を深めてください。
高額療養費制度とは?〜医療費の自己負担を軽くする制度〜
高額療養費制度とは、1ヶ月(月の初めから終わりまで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
私たちは通常、国民健康保険や会社の健康保険などの公的医療保険に加入しており、医療機関の窓口で支払う医療費は、かかった費用の原則1割〜3割です。しかし、手術や長期入院などで医療費が高額になると、この自己負担分だけでも大きな金額になってしまいます。
高額療養費制度は、そのような医療費の負担が家計を圧迫しすぎないように設けられた、セーフティネットの役割を果たしています。
ポイント:
- 1ヶ月の医療費が対象(月の1日〜末日まで)。
- 自己負担限度額を超えた分が払い戻される。
- 公的医療保険(健康保険)の制度の一つ。
いくらまで自己負担?自己負担限度額について
では、具体的にいくらまで自己負担すれば良いのでしょうか?この「自己負担限度額」は、**年齢(70歳未満か、70歳以上か)**と、**所得(収入)**によって細かく区分されています。
【70歳未満の方の自己負担限度額(月額)】
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 多数回該当※ |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) × 1% | 140,100円 |
| 年収約770万~約1,160万円 | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) × 1% | 93,000円 |
| 年収約370万~約770万円 | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) × 1% | 44,400円 |
| ~年収約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
※多数回該当:過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から上限額が下がります。
【70歳以上の方の自己負担限度額(月額)】
70歳以上の方は、さらに細かく区分されます。
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 入院・世帯ごと |
|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ (年収約1,160万円~) | 252,600円 + (医療費 – 842,000円) × 1% (多数回該当 140,100円) | |
| 現役並み所得者Ⅱ (年収約770万~約1,160万円) | 167,400円 + (医療費 – 558,000円) × 1% (多数回該当 93,000円) | |
| 現役並み所得者Ⅰ (年収約370万~約770万円) | 80,100円 + (医療費 – 267,000円) × 1% (多数回該当 44,400円) | |
| 一般 (年収約156万~約370万円) | 18,000円 | 57,600円 (多数回該当 44,400円) |
| 住民税非課税等Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 住民税非課税等Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
(注)
- 上記の表は一般的な目安です。正確な区分や金額は、ご自身が加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険など)にご確認ください。
- 「医療費」とは、保険適用される医療費の総額(10割分)です。
- 所得区分は、標準報酬月額や課税所得などによって判定されます。
《かんたん計算例(70歳未満・年収約500万円の方の場合)》
- 所得区分:「年収約370万~約770万円」
- 自己負担限度額の計算式:80,100円 + (医療費 – 267,000円) × 1%
- 1ヶ月の医療費(10割)が100万円だった場合
- 窓口負担(3割):30万円
- 自己負担限度額:80,100円 + (1,000,000円 – 267,000円) × 1% = 87,430円
- 高額療養費として払い戻される額:300,000円 – 87,430円 = 212,570円
この例の場合、窓口で30万円支払いますが、後で申請すれば約21万円が戻ってくる計算になります。
対象となる医療費・ならない医療費
高額療養費制度の対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費に限られます。
【対象となる費用の例】
- 保険診療にかかる診察費、検査費、処置費、手術費、入院費
- 処方された薬代
【対象とならない費用の例】
- 入院時の食事代(標準負担額)
- 差額ベッド代(個室など希望した場合)
- 保険適用外の診療(自由診療、美容整形など)
- 先進医療にかかる費用(技術料)
- 文書料(診断書など)
- 予防接種
- 健康診断
これらは全額自己負担となり、高額療養費の計算には含まれませんので注意が必要です。
申請方法と流れ〜どうすればお金が戻ってくる?〜
高額療養費の支給を受けるには、原則として申請が必要です。申請方法は大きく分けて2つあります。
1. 事後申請(お金が戻ってくる方法)
医療機関の窓口でいったん自己負担分(1割〜3割)を支払い、後日、加入している公的医療保険の窓口(保険者)に申請して、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受ける方法です。
- 申請先: ご自身が加入している公的医療保険の窓口
- 国民健康保険 → お住まいの市区町村役場
- 協会けんぽ → 全国健康保険協会(協会けんぽ)の支部
- 組合健保 → 勤務先の健康保険組合
- 共済組合 → 各共済組合
- 後期高齢者医療制度 → お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口
- 必要なもの(主なもの):
- 高額療養費支給申請書(申請窓口で入手または郵送、Webサイトからダウンロードできる場合も)
- 医療機関の領収書(原本が必要な場合が多い)
- 保険証
- 振込先口座の情報がわかるもの(通帳など)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類
- 申請期限: 診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。期限を過ぎると払い戻しを受けられなくなるので注意しましょう。
- 支給時期: 申請してから実際に振り込まれるまで、通常3ヶ月以上かかることが多いです。
自動で通知が来る場合も: 加入している保険によっては、高額療養費の対象になった場合に、申請を促す通知や申請書が自動的に送られてくることがあります。しかし、必ず送られてくるわけではないので、高額な医療費がかかった場合は、自分から確認・申請することをおすすめします。
2. 事前申請(窓口での支払いを抑える方法)
あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができる方法です。
- メリット: 一時的な高額な立て替え払いが不要になります。
- 申請先: 事後申請と同じく、加入している公的医療保険の窓口。
- 申請方法: 各保険者の窓口や郵送で申請します。
- 必要なもの: 申請書、保険証など(詳細は加入保険者へ確認)。
- 注意点:
- 事前に申請・交付が必要です。入院や手術の予定が決まったら早めに手続きしましょう。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録(マイナ保険証)している場合、医療機関が対応していれば、限度額適用認定証がなくても自動的に窓口での支払いが限度額までになることがあります。(※ただし、非課税世帯の方などは別途認定証が必要な場合や、医療機関側のシステム対応状況によります。)
どちらの方法が良い?
- 入院や手術などで高額な医療費がかかることが事前にわかっている場合は、「限度額適用認定証」の事前申請がおすすめです。一時的な負担を大きく減らせます。
- 予期せぬ病気やケガで急に医療費が高額になった場合や、複数の医療機関にかかって結果的に高額になった場合は、事後申請で払い戻しを受けます。
知っておくとお得!負担をさらに軽減する仕組み
高額療養費制度には、さらに自己負担を軽減するための仕組みがあります。
1. 世帯合算
一人分の窓口負担では自己負担限度額を超えない場合でも、**同じ月内に、同じ医療保険に加入している家族(世帯)**の自己負担額を合算することができます。
合算できるのは、1件あたり21,000円以上の自己負担額(70歳未満の場合)です。70歳以上の場合は、金額に関わらず全ての自己負担額を合算できます。
合算した結果、世帯全体の自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。
例: 夫:A病院で30,000円の自己負担 妻:B病院で40,000円の自己負担 → 世帯で合計70,000円の自己負担。 この世帯の自己負担限度額が57,600円の場合、70,000円 – 57,600円 = 12,400円が払い戻されます。
ポイント:
- 同じ医療保険に加入している家族が対象。
- 同じ月内の自己負担額を合算。
- 70歳未満は、1件21,000円以上の自己負担のみ合算可能。
2. 多数回該当
過去12ヶ月以内に、高額療養費の支給を3回以上受けた場合、4回目からは自己負担限度額がさらに引き下げられます。これを「多数回該当」といいます。
これにより、長期にわたって高額な治療が必要な方の負担が軽減されます。(具体的な金額は前述の自己負担限度額の表を参照)
よくある質問(Q&A)
Q1. 申請はいつまでにすればいいですか? A1. 診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。期限を過ぎると時効となり申請できなくなります。
Q2. 申請してから、いつ頃お金は振り込まれますか? A2. 加入している保険者や審査状況によって異なりますが、一般的に申請から3ヶ月以上かかることが多いです。詳しくは申請時に確認しましょう。
Q3. 自分の所得区分はどうやって確認できますか? A3. 加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保、市区町村の国保窓口など)にお問い合わせください。保険証や、送られてくる通知書などで確認できる場合もあります。
Q4. 転職して健康保険が変わった場合はどうなりますか? A4. 高額療養費は、診療を受けた時点で加入していた健康保険に申請します。転職前の分は前の健康保険へ、転職後の分は新しい健康保険へそれぞれ申請が必要です。世帯合算や多数回該当も、同じ健康保険に加入している期間で計算されます。
Q5. 引っ越して国民健康保険の市区町村が変わった場合は? A5. 転職の場合と同様に、診療を受けた時点で加入していた市区町村の国民健康保険に申請します。
まとめ:いざという時のために、制度を理解しておこう
高額療養費制度は、予期せぬ病気やケガによる高額な医療費負担から、私たちの家計を守ってくれる大切な制度です。
- 1ヶ月の自己負担には上限があること
- 上限額は年齢と所得で決まること
- 超えた分は申請すれば払い戻されること(または事前に支払いを抑えられること)
- 世帯合算や多数回該当でさらに負担が軽くなる場合があること
これらのポイントを押さえておけば、いざという時に慌てず、安心して医療を受けることができます。
ご自身の正確な自己負担限度額や申請方法について不明な点があれば、必ず加入している公的医療保険の窓口(保険証に記載の保険者)に確認するようにしましょう。
この記事が、高額療養費制度の理解の一助となれば幸いです。
この記事を書いた人:かんとりー(ファイナンシャルプランナー2級)
節約・投資・デジタル活用を中心に、暮らしに役立つ情報を発信中。
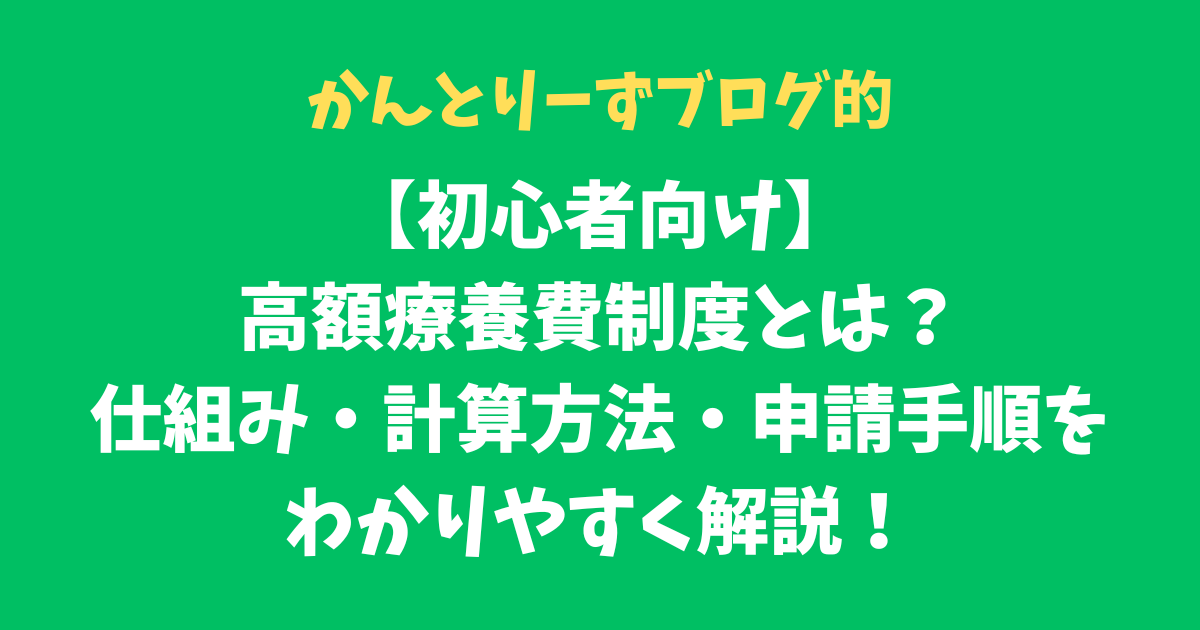
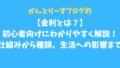
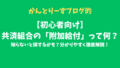
コメント