「株価は長期的には右肩上がりに上昇する」 「だから、株式投資は早く始めた方がいい」
このような言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?実際に、過去のデータを見ると、多くの国の株式市場は長期的に上昇傾向を示しています。しかし、「上がり続ける」という言葉を鵜呑みにしてしまうのは危険です。
この記事では、「株価は上がり続ける」と言われる根拠はどこにあるのか、そして投資をする上で知っておくべきリスクや注意点について、わかりやすく解説します。
なぜ株価は長期的に上昇する傾向にあるのか?その根拠とは
株価が短期的に上下することは日常茶飯事ですが、数十年単位の長い目で見ると上昇傾向にあるとされるのには、主に以下のような経済的な根拠があります。
- 経済成長と企業価値の向上:
- 世界経済は、人口増加や技術革新などを背景に、長期的には成長を続けてきました。
- 経済が成長すると、企業の売上や利益も増加する傾向にあります。
- 企業の利益が増えれば、その企業の価値(企業価値)も高まり、それが株価に反映されると考えられます。つまり、経済全体のパイが大きくなることで、株価も上昇していくという仕組みです。
- インフレーション(物価上昇)の影響:
- 多くの国では、経済成長とともに緩やかなインフレーション(物価上昇)が起こります。
- 物価が上昇すると、企業の持つ資産の価値や、製品・サービスの価格も名目上は上昇します。
- これにより、企業の売上や利益も名目上は増加し、株価を押し上げる要因の一つとなります。現金(貯金)はインフレによって実質的な価値が目減りする可能性がありますが、株式はインフレに強い資産と言われることがあります。
- 技術革新と生産性の向上:
- インターネット、AI、再生可能エネルギーなど、新しい技術は次々と生まれ、社会や産業のあり方を大きく変えてきました。
- 技術革新は、企業の生産性を向上させ、新しい市場を創出し、利益成長の源泉となります。
- こうしたイノベーションへの期待感が、株価を押し上げる力となります。
- 配当再投資の効果(複利効果):
- 企業は利益の一部を株主へ配当金として還元します。
- この配当金を使わずに、再び株式の購入に充てる(配当再投資)ことで、雪だるま式に資産が増えていく「複利効果」が期待できます。
- 長期的に配当再投資を続けることで、当初の投資元本だけでなく、配当金が生み出した利益もさらに利益を生むようになり、株価上昇とは別の形でも資産形成に貢献します。
これらの要因が複合的に作用することで、株価は短期的な変動を繰り返しながらも、長期的には上昇する傾向が見られるのです。
短期・中期的な株価上昇の要因(ただし注意が必要)
長期的な上昇傾向とは別に、数ヶ月〜数年単位で株価を押し上げる要因も存在します。
- 金融緩和: 中央銀行が金利を引き下げたり、市場にお金を供給したりする政策(金融緩和)は、企業が資金を借りやすくなり、設備投資や事業拡大を後押しします。また、低い金利は預貯金の魅力を相対的に低下させ、株式市場へ資金が流れ込みやすくなる傾向があります。
- 財政政策: 政府による減税や公共投資といった景気刺激策は、企業業績や個人消費を押し上げ、株価にとってプラス要因となることがあります。
- 良好な企業業績: 個別企業や特定のセクターの業績が市場の予想を上回ると、その企業の株価は評価されやすくなります。経済全体の景気が良い局面では、多くの企業の業績が向上し、市場全体の株価を押し上げることがあります。
- 市場心理(センチメント): 投資家の間で楽観的な見方が広がると、「これから株価が上がるだろう」という期待から買いが集まりやすくなり、実際の株価上昇につながることがあります。(逆も然りです)
【重要】短期・中期的な要因に関する注意点 これらの要因は、経済状況や政策判断、市場の雰囲気によって常に変化します。金融緩和はいずれ引き締めに転じますし、景気刺激策がいつまでも続くわけではありません。企業業績も景気循環の影響を受けます。市場心理は些細なニュースで急変することもあります。
したがって、これらの短期・中期的な要因だけを見て「株価は上がり続ける」と判断するのは非常に危険です。短期的な市場の方向性を正確に予測することはプロでも困難です。
「株価は上がり続ける」という考え方のリスクと注意点
「株価は長期的には上昇する傾向がある」というのは事実ですが、「常に」「一本調子で」上がり続けるわけでは決してありません。投資を行う上で、以下のリスクを十分に理解しておく必要があります。
- 「常に」上がり続けるわけではない(下落局面は必ずある):
- 歴史を振り返れば、○○ショックと呼ばれるような株価の暴落は何度も起きています。短期間で株価が半分以下になることも珍しくありません。
- 「長期的に見れば上がるから」と考えても、下落局面で精神的に耐えられなくなって売却してしまう(狼狽売り)と、損失を確定させてしまいます。
- 景気後退(リセッション)のリスク:
- 経済には好況と不況の波があります。景気が後退局面に入ると、企業の業績が悪化し、株価は大きく下落する可能性があります。
- 金融引き締めへの転換リスク:
- インフレが過熱した場合、中央銀行は金利を引き上げて経済を冷まそうとします(金融引き締め)。金利上昇は企業の資金調達コストを増加させ、株式市場にとっては逆風となります。
- 地政学的リスク:
- 戦争、紛争、テロ、貿易摩擦、政治的な不安定さなどは、市場の先行き不透明感を高め、投資家心理を悪化させ、株価下落の要因となります。これらの出来事を予測することは極めて困難です。
- バブルとその崩壊のリスク:
- 時に、株価は企業の実態価値や経済の状況からかけ離れて、期待感だけで異常なほど上昇することがあります(バブル)。バブルはいつか必ず弾け、その後の株価急落(クラッシュ)を招きます。
- 個別企業の要因によるリスク:
- 市場全体が好調でも、特定の企業が業績不振に陥ったり、不祥事を起こしたりすれば、その企業の株価は大きく下落する可能性があります。最悪の場合、倒産して株の価値がゼロになることもあります。
このように、株式投資には様々なリスクが伴います。「株価は上がり続ける」という言葉のポジティブな側面だけを見るのではなく、こうしたリスクを理解し、備えることが重要です。
株価変動を前提とした賢明な投資戦略
では、株価の変動リスクとどう向き合えば良いのでしょうか。以下に、基本的な投資戦略の考え方を示します。
- 長期的な視点を持つ:
- 短期的な株価の上下に一喜一憂せず、数年~数十年単位での資産形成を目指しましょう。歴史が示すように、長期で見れば経済成長の恩恵を受けられる可能性が高まります。
- 分散投資を心がける:
- 「卵は一つのカゴに盛るな」という格言の通り、投資先を一つの銘柄や国、資産クラス(株式だけでなく債券や不動産など)に集中させず、複数に分散させることが重要です。これにより、特定の投資先が下落した場合のリスクを軽減できます。
- 自身のリスク許容度を把握する:
- 投資でどれくらいの損失までなら精神的・経済的に耐えられるか(リスク許容度)を把握しましょう。リスク許容度は年齢、収入、資産状況、性格などによって異なります。自分のリスク許容度を超えた投資は避けましょう。
- 積立投資を活用する:
- 毎月一定額を定期的に購入していく「積立投資」は、購入タイミングを分散させる効果があります。株価が高い時には少なく、安い時には多く購入できるため、平均購入単価を抑える効果(ドルコスト平均法)が期待でき、高値掴みのリスクを減らすことができます。
まとめ
「株価は上がり続ける」という言葉には、経済成長やインフレ、技術革新といった長期的な上昇を支える根拠があります。過去のデータも、株式市場が長期的に右肩上がりの傾向にあることを示しています。
しかし、それは**「常に」「一本調子で」上がり続けるという意味ではありません**。株価には必ず変動があり、時には暴落と呼ばれるような大きな下落も経験します。景気後退、金融政策の転換、地政学的リスクなど、株価を下落させる要因も数多く存在します。
株式投資を行う際には、「上がり続ける」という言葉の楽観的な側面だけでなく、必ず伴うリスクを十分に理解することが不可欠です。そして、そのリスクと上手に付き合っていくために、「長期」「分散」「積立」といった基本的な投資戦略を心がけ、ご自身のリスク許容度の範囲内で行うことが、賢明な資産形成への道と言えるでしょう。
この記事が、あなたの株式投資に対する理解を深める一助となれば幸いです。
この記事を書いた人:かんとりー(ファイナンシャルプランナー2級)
節約・投資・デジタル活用を中心に、暮らしに役立つ情報を発信中。
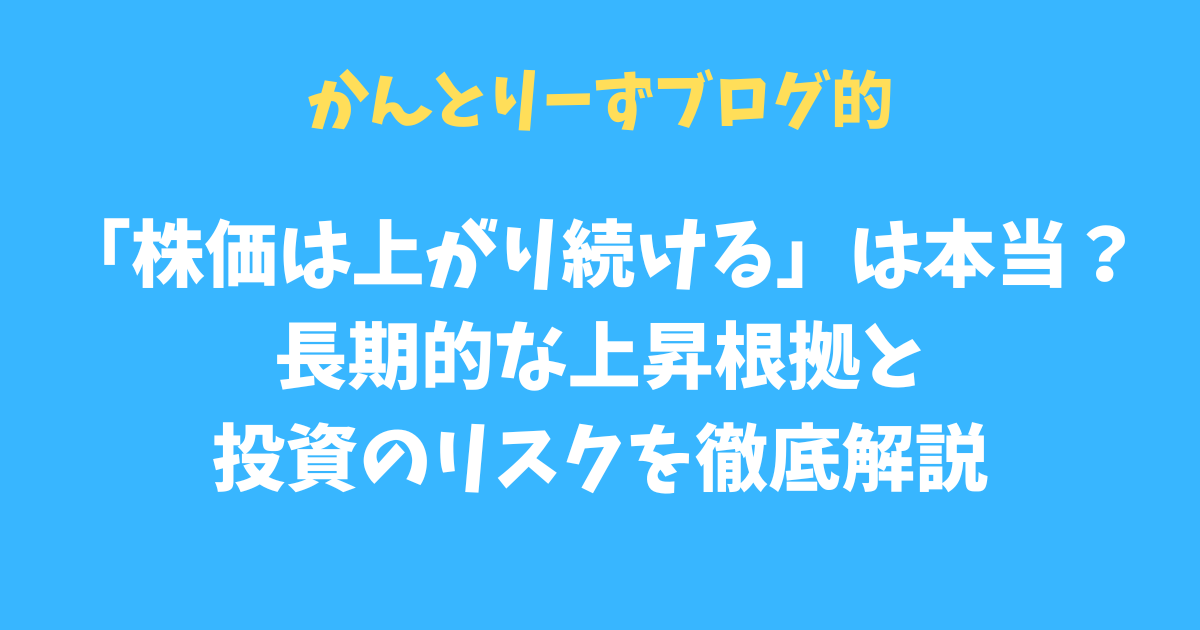
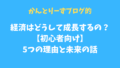
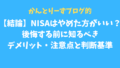
コメント