「金利ってよく聞くけど、なんだか難しそう…」「ニュースで金利が上がった下がったと言っているけど、どういう意味?」
そんな疑問をお持ちではありませんか? 金利は、私たちのお金の貸し借りや預金に深く関わる、とても大切な仕組みです。
この記事では、「金利」について、専門用語をできるだけ使わずに、初心者の方にもわかりやすく解説します。この記事を読めば、金利の基本的な意味から、種類、決まり方、そして私たちの生活にどう影響するのかがスッキリ理解できます。
金利とは?一言でいうと「お金のレンタル料」
金利を一言で表すと、**「お金を貸し借りする際のレンタル料(利用料)」**のようなものです。
- お金を借りる人: お金を借りた期間や金額に応じて、レンタル料(=利息)を支払います。
- お金を貸す人(預ける人): お金を貸した(預けた)期間や金額に応じて、レンタル料(=利息)を受け取ります。
このレンタル料(利息)を計算するための「割合」が**金利(利率)**です。通常、「年利〇%」のように、1年間に対する割合で示されます。
【基本用語】
- 元本(がんぽん): 貸し借りする元のお金。
- 利息(りそく): 元本に対して支払われたり、受け取ったりするお金(レンタル料)。
- 金利(きんり)・利率(りりつ): 元本に対する利息の割合(レンタル料率)。
例:100万円を年利3%で1年間借りた場合
- 元本:100万円
- 金利(年利):3%
- 1年間の利息:100万円 × 3% = 3万円
- 返済総額:100万円(元本) + 3万円(利息) = 103万円
銀行にお金を預ける(=銀行にお金を貸す)場合も同じで、預けたお金(元本)に対して、銀行が定める金利に応じた利息が支払われます。
なぜ金利が必要なの?
では、なぜお金の貸し借りに金利が必要なのでしょうか?主な理由は以下の3つです。
- お金の時間的価値: 今すぐ使える1万円と、1年後に手に入る1万円では、価値が異なります。今すぐ使えれば、何かを買ったり、運用して増やしたりできる可能性があります。お金を貸す人は、その「今すぐ使えたはずの価値」を手放す対価として利息を求めます。
- 信用リスク: お金を貸した相手が、約束通りに返してくれない可能性があります(貸し倒れリスク)。貸し手は、そのリスクを引き受ける対価として利息を上乗せします。
- インフレリスク: 物価が上昇する(インフレ)と、お金の価値は実質的に目減りします。例えば、今日100円で買えたものが、1年後には105円出さないと買えなくなるかもしれません。貸し手は、将来お金が返ってきたときに価値が下がっている可能性を考慮して、利息を求めます。
金利の主な種類:「単利」と「複利」
金利の計算方法には、大きく分けて「単利」と「複利」の2種類があります。これは、特にお金を預けたり、長期間借りたりする場合に重要なので、しっかり理解しておきましょう。
単利(たんり)
単利とは、最初に預けた元本に対してのみ利息が計算される方法です。
例:100万円を年利3%(単利)で3年間預けた場合
- 1年目の利息:100万円 × 3% = 3万円 → 合計103万円
- 2年目の利息:100万円 × 3% = 3万円 → 合計106万円
- 3年目の利息:100万円 × 3% = 3万円 → 最終合計 109万円
毎年もらえる利息の額は変わりません。
複利(ふくり)
複利とは、元本だけでなく、それまでに付いた利息にも次の期間の利息が付く計算方法です。利息が利息を生む、「雪だるま式」に増えていくイメージです。
例:100万円を年利3%(複利)で3年間預けた場合
- 1年目の利息:100万円 × 3% = 3万円 → 年末残高 103万円
- 2年目の利息:103万円 × 3% = 3万900円 → 年末残高 106万900円
- 3年目の利息:106万900円 × 3% = 3万207円 → 最終合計 109万2,727円
単利の場合(109万円)と比べて、複利の方が最終的な受取額が多くなります。期間が長くなるほど、この差は大きくなります。
**「複利は人類最大の発明だ」**とアインシュタインが言ったとされるほど、長期的な資産形成において複利の効果は絶大です。逆に、借金で複利が適用されると、返済額が大きく膨らむ可能性があるので注意が必要です。
金利はどうやって決まるの?
金利は様々な要因によって変動します。主な要因を見てみましょう。
- 日本銀行の金融政策: 日本の中央銀行である日本銀行が決定する「政策金利」は、銀行間の短期的なお金の貸し借り金利の目標です。これが引き上げられると、銀行が企業や個人にお金を貸し出す際の金利も上昇する傾向があり、逆もまた然りです。景気が過熱しているときは金利を上げて経済活動を抑え、景気が悪いときは金利を下げて経済活動を刺激しようとします。
- 景気の動向: 景気が良いと、企業は設備投資のため、個人は住宅購入などのためにお金を借りる需要が増えます。お金を借りたい人が増えると、金利は上昇しやすくなります。逆に景気が悪いと、お金の需要が減り、金利は低下しやすくなります。
- 物価の変動(インフレ・デフレ): 物価が継続的に上昇するインフレが予想される場合、お金の価値が目減りするため、金利は上昇する傾向があります。逆に物価が下落するデフレの場合は、金利は低下しやすくなります。
- 為替相場: 円安が進むと輸入品の価格が上がり、インフレ懸念から金利が上昇する可能性があります。
- 海外の金利動向: グローバル経済においては、特にアメリカなど主要国の金利動向が日本の金利にも影響を与えます。
個別のローン(住宅ローンやカードローンなど)の金利は、これらの市場全体の金利動向に加えて、借りる人の信用力(返済能力や過去の借入履歴など)や、借入期間、担保の有無なども考慮されて決定されます。
金利が私たちの生活に与える影響
金利の変動は、私たちの生活の様々な場面に影響を与えます。
お金を借りるとき(住宅ローン、自動車ローン、カードローンなど)
- 金利が上昇すると…
- 毎月の返済額や総返済額が増える。
- 特に変動金利型のローンを組んでいる場合、返済負担が重くなる可能性がある。
- これからローンを組む場合、借りにくくなる、または希望額を借りられなくなる可能性がある。
- 金利が低下すると…
- 毎月の返済額や総返済額が減る。
- ローンを借りやすくなる。
- 固定金利から低い変動金利への借り換えを検討するチャンス。
お金を預ける・増やすとき(預金、債券など)
- 金利が上昇すると…
- 銀行預金(普通預金、定期預金など)で受け取れる利息が増える。
- 新しく発行される債券の利率(クーポン)が高くなる傾向がある。
- 金利が低下すると…
- 銀行預金で受け取れる利息が減る(ゼロに近い状態が続くことも)。
- 新しく発行される債券の利率が低くなる傾向がある。
経済全体への影響
金利は、企業や個人の消費・投資活動を通じて、経済全体にも影響を与えます。
- 金利上昇 → 借入コスト増 → 企業の設備投資や個人の消費が抑制される → 景気減速の可能性
- 金利低下 → 借入コスト減 → 企業の設備投資や個人の消費が促進される → 景気回復の可能性
まとめ:金利を理解して、賢くお金と付き合おう!
今回は「金利」について、基本的な意味から種類、決まり方、生活への影響までをわかりやすく解説しました。
- 金利とは「お金のレンタル料(の割合)」
- お金を借りれば支払い、預ければ受け取るのが「利息」
- 利息の付き方には「単利」と「複利」があり、特に複利は長期で大きな差を生む
- 金利は日銀の政策や景気、物価など様々な要因で変動する
- 金利の変動は、ローン返済や預金利息など、私たちの生活に直接影響する
金利は、一見難しく感じるかもしれませんが、仕組みを理解すれば、住宅ローンの選択や貯蓄・投資の方法を考える上で、必ず役立ちます。ニュースなどで金利の話題が出たときも、その意味や影響をイメージしやすくなるはずです。
この記事が、あなたの「金利 わかりやすく知りたい!」という疑問を解消する一助となれば幸いです。
この記事を書いた人:かんとりー(ファイナンシャルプランナー2級)
節約・投資・デジタル活用を中心に、暮らしに役立つ情報を発信中。
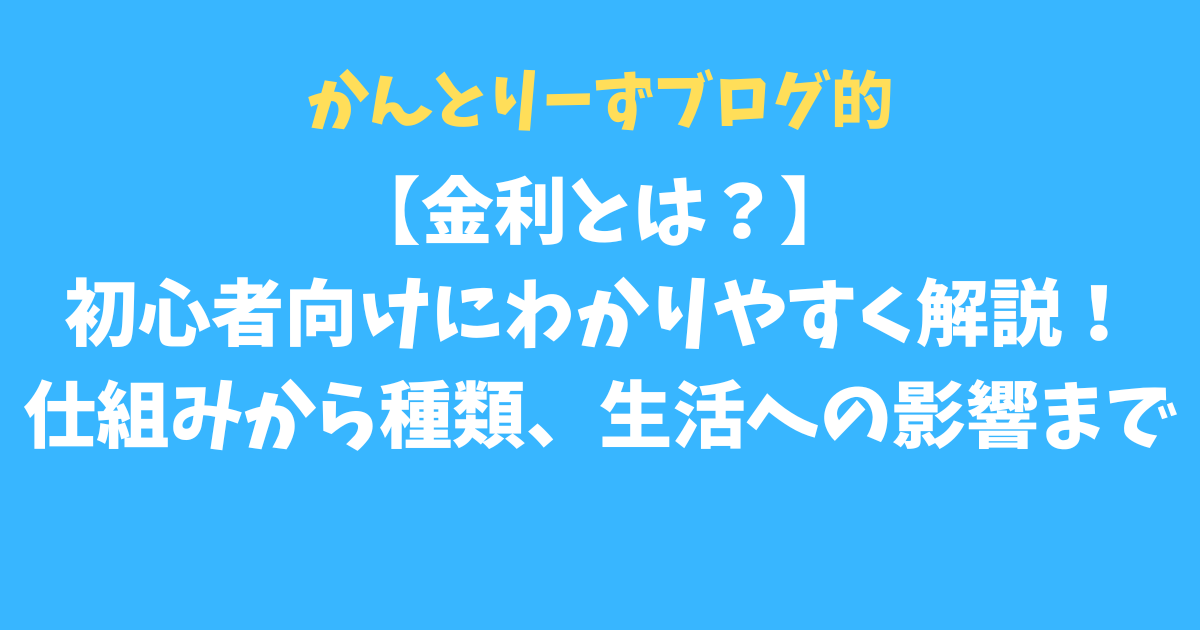
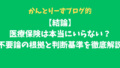
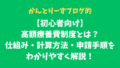
コメント