「医療保険って、本当に入る必要あるの?」「公的な保険で十分じゃない?」
近年、「医療保険はいらない」という声を耳にする機会が増えました。実際に、日本の公的医療保険制度は充実しており、「高額療養費制度」などを活用すれば、医療費の自己負担はある程度抑えられます。
しかし、本当にすべての人にとって医療保険が不要なのでしょうか?
この記事では、「医療保険はいらない」と言われる理由、それでも医療保険が必要になるケース、そしてご自身にとって必要かどうかを判断するための基準について、分かりやすく解説します。
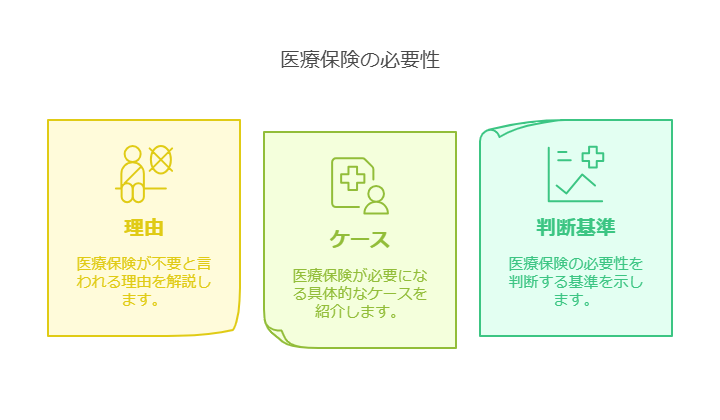
この記事を読むことで、以下の点が理解できます。
- なぜ「医療保険はいらない」という意見があるのか?(不要論の根拠)
- 公的医療保険だけではカバーしきれないリスクとは?
- 自分にとって医療保険が必要かどうかの判断基準
- 医療保険以外の選択肢
結論から言うと、「医療保険が必要かどうか」は、個人の貯蓄状況、ライフステージ、価値観によって異なります。
この記事を読んで、ご自身の状況に合った最適な判断をするための一助となれば幸いです。
なぜ「医療保険はいらない」と言われるのか?主な理由3つ
医療保険が不要だと考える主な根拠は、日本の手厚い公的医療保険制度にあります。
- 国民皆保険制度による自己負担割合の軽減:
- 日本では、すべての国民が何らかの公的医療保険(国民健康保険、社会保険など)に加入しています。
- 医療機関にかかった際の自己負担は、年齢や所得に応じて原則1割〜3割に抑えられています。
- つまり、医療費全額を負担する必要はありません。
- 高額療養費制度の存在:
- 医療費の自己負担額が、1ヶ月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。
- 上限額は年齢や所得区分によって異なりますが、例えば一般的な所得(年収約370~約770万円)の方であれば、月々の医療費負担は約8万円+α程度で済みます(※)。
- この制度により、高額な治療を受けたとしても、自己負担額が青天井になることはありません。
- (※)詳しい計算方法や所得区分は、厚生労働省などの公式サイトでご確認ください。
- 貯蓄で十分に対応できるという考え:
- 上記の制度を踏まえ、「もし病気やケガをしても、数十万円程度の貯蓄があれば、当面の医療費は賄える」と考える人もいます。
- 毎月保険料を払い続けるよりも、その分を貯蓄や投資に回した方が合理的だという判断です。
これらの理由から、「わざわざ民間の医療保険に加入しなくても、公的保険と貯蓄で十分対応できる」という考え方が、「医療保険不要論」の根拠となっています。
それでも医療保険を検討すべき理由|公的保険の範囲外と注意点
公的医療保険制度は非常に優れていますが、万能ではありません。以下の点は、医療保険の必要性を考える上で重要なポイントです。
- 公的医療保険の対象外となる費用:
- 差額ベッド代: 個室や少人数の病室を利用した場合にかかる費用。公的保険の対象外で、全額自己負担となります。(1日あたり数千円〜数万円かかることも)
- 先進医療にかかる技術料: 公的保険の対象外となっている高度な医療技術。技術料は全額自己負担となり、中には数百万円以上かかるものもあります。
- 入院中の食事代(一部)や日用品費、交通費など: 治療に直接関係ない費用も自己負担です。
- 一部の歯科治療や美容目的の治療など
- 収入減のリスク:
- 病気やケガで長期間働けなくなった場合、収入が途絶える可能性があります。
- 会社員などであれば「傷病手当金」が支給される場合もありますが、自営業者や非正規雇用の方はない場合が多く、また支給額も収入全額をカバーするものではありません。
- 医療費そのものだけでなく、生活費の補填という意味合いで、給付金が出るタイプの医療保険が役立つケースがあります。
- 貯蓄を取り崩すことへの抵抗感・不安:
- 「貯蓄で対応できる」と考えていても、実際にまとまった額の貯蓄を取り崩すことには精神的な負担が伴います。
- 特に、その貯蓄が住宅購入や子供の教育費など、他の目的のために準備していたものだった場合、将来設計に影響が出る可能性もあります。
- 精神的な安心感:
- 「もしもの時に備えがある」という安心感は、日々の生活を送る上で大きな支えになります。
- 医療保険に加入していることで、経済的な心配をせずに治療に専念できるというメリットがあります。
- 加入したい時に加入できない可能性:
- 医療保険は、健康状態によっては加入できなかったり、特定の病気が保障対象外になるなどの条件が付くことがあります。
- 「必要性を感じてから加入しよう」と思っても、その時には希望通りの保険に入れない可能性があることは、考慮しておくべき点です。
あなたに医療保険は必要?不要?判断するためのチェックリスト
結局のところ、医療保険が必要かどうかは、個々の状況によって異なります。以下の点を考慮して、ご自身で判断してみましょう。
- □ 貯蓄は十分にあるか?
- 目安として、万が一の入院や手術があっても、当面の医療費(高額療養費制度利用後の自己負担額+α)や、数ヶ月分の生活費を賄えるだけの貯蓄がありますか? (例:100万円〜200万円程度)
- □ 公的医療保険制度(特に高額療養費制度)を理解しているか?
- ご自身の所得区分での自己負担上限額を把握していますか?
- □ 家族構成やライフステージは?
- 扶養している家族はいますか? ご自身が倒れた場合に、家計への影響が大きい立場ですか?
- □ 健康状態や将来のリスクに対する考え方は?
- 現在健康ですか? 将来の病気リスクに対して、どの程度備えたいと考えていますか?
- 多少の自己負担は許容できますか? それとも、可能な限り自己負担を抑えたいですか?
- □ 差額ベッド代や先進医療への備えは必要と考えるか?
- 万が一の際に、より快適な入院環境や最新の治療を選択したいと考えますか?
- □ 保険料を負担に感じるか?
- 毎月の保険料を支払うことに、経済的・精神的な負担を感じますか?
これらの質問に対して、不安を感じる項目がある方は、医療保険への加入を検討する価値があるでしょう。
医療保険以外の選択肢
医療保険の代わりに、以下のような方法で備えることも可能です。
- 貯蓄の強化: 最も基本的な備えです。目標額を設定し、計画的に貯蓄を進めましょう。
- 就業不能保険: 病気やケガで働けなくなった場合の収入減に特化して備える保険です。
- 共済: 営利を目的としないため、比較的掛金が安い場合があります。保障内容はよく確認しましょう。
- 資産運用: 保険料に相当する金額を投資に回し、将来の医療費に備えるという考え方もありますが、元本割れのリスクも伴います。
まとめ:医療保険の必要性は人それぞれ。情報を元に最適な判断を
「医療保険はいらない」という意見には、日本の充実した公的医療保険制度という確かな根拠があります。高額療養費制度などを活用すれば、医療費の自己負担は一定額に抑えられます。
一方で、差額ベッド代や先進医療、働けなくなった場合の収入減など、公的保険だけではカバーしきれないリスクも存在します。
最終的に医療保険が必要かどうかは、あなたの貯蓄額、家族構成、健康状態、そして何より「安心」に対する価値観によって決まります。
「いらない」と決めつける前に、まずは公的制度を正しく理解し、ご自身の状況と照らし合わせて、本当に不要なのか、それとも何らかの備えが必要なのかを冷静に判断することが重要です。
この記事が、あなたの選択の一助となれば幸いです。
この記事を書いた人:かんとりー(ファイナンシャルプランナー2級)
節約・投資・デジタル活用を中心に、暮らしに役立つ情報を発信中。
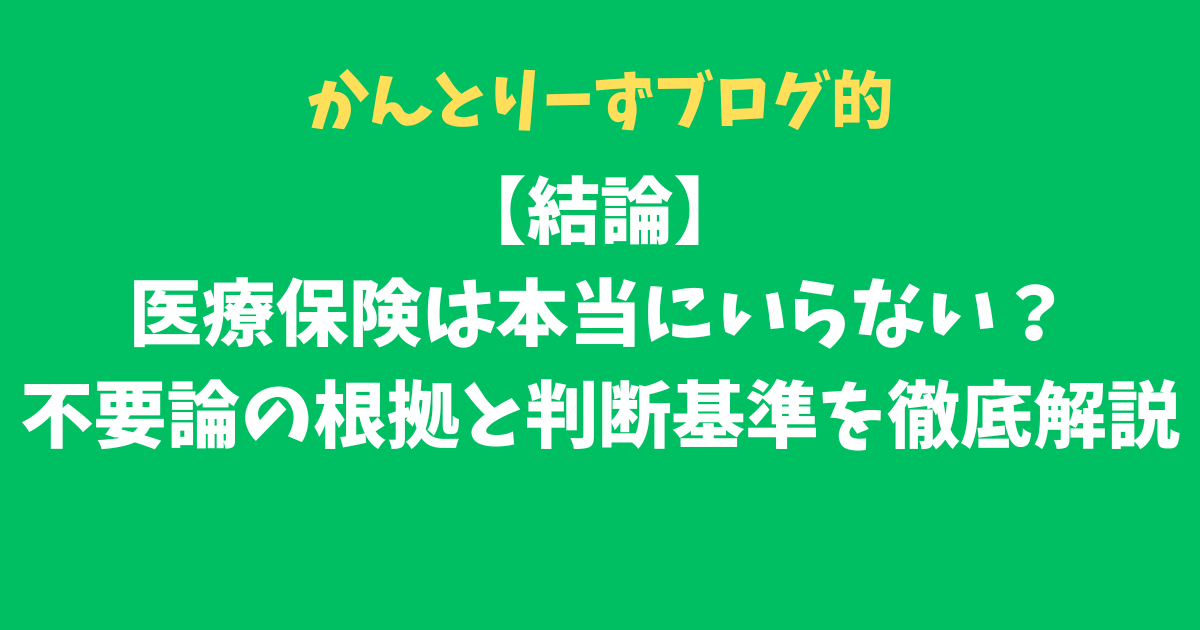
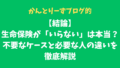
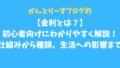
コメント